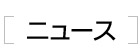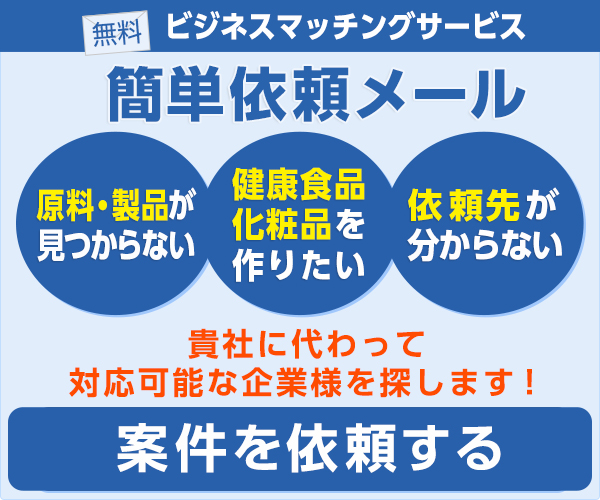京都大学生態学研究センター 工藤洋 教授、永野惇 同研究員(研究当時、現 龍谷大学講師)、本庄三恵 同研究員らのグループは、植物の葉で機能している全遺伝子を対象に、毎週 2 年間にわたって遺伝子の働きを測定しました。
測定は、日本に自生する植物であるアブラナ科のハクサンハタザオについて、兵庫県多可郡多可町中区牧野および門前にある同植物の自然生育地において実施されました。その結果、葉で働いていた 17,205種類の遺伝子のうち、16.7%にあたる 2,879 の遺伝子が季節に応じてその働きの強さを変化させることを明らかにしました。また、春分・夏至・秋分・冬至での日内変化を調べ、7,185 の遺伝子が 1 日のうちで働きの強さを変化させることも明らかにしました。
これまで主に実験室環境で研究されてきた遺伝子が、自然条件下で日内変化を示すもの、季節変化を示すもの、変化せずに働き続けるものに分類されました。同研究において、季節変化することが初めて明らかになった遺伝子も多数ありました。全遺伝子の働きの同時測定という最新の分子遺伝学の手法と、自然生育地の毎週調査という地道な生態学の手法とを組み合わせることが新たな成果につながりました。同研究は年間を通して網羅的に遺伝子の働きの季節変化を明らかにした初めての例であり、その成果として季節変化を示す遺伝子がカタログ化され簡単に検索できるようになります。同研究成果は、2019 年1月 8 日に国際学術誌「Nature Plants」にオンライン掲載されました。
■1.背景■
日本を含む温帯域において、環境のもっとも顕著な変化は季節として現れます。そのため、植物をはじめとするほとんどの生物が、季節に応じた生活のスケジュールを持っています。植物が決まった時期に葉を開き、花を咲かせ、種子を実らせ、葉を落とすのがその例です。最近の研究手法の発達により、野外における遺伝子の働きを測定することが可能となりました。それに伴い、遺伝子の機能を明らかにするうえでも、本来の生育地で研究をすることが重要となりました。そこで、次世代シーケンサを用いることにより、全ての遺伝子の働きについて、その季節変化を測定することを目的とした本プロジェクトがはじまりました。
■2.研究手法・成果■
植物は移動しないので、自然条件下での継続観察が可能であるという利点がありました。また、野生植物をその自然生育地において研究することが、本来の季節性を観測するという点で重要となります。日本に自生する植物であるアブラナ科の常緑多年生草本ハクサンハタザオについて、兵庫県多可郡多可町中区牧野および門前にある同植物の自然生育地を、毎週 2 年間にわたって調査し、葉を採集して、遺伝子の働きを調べました。遺伝子が働くときに作られる分子であるメッセンジャーRNA を取り出し、対応する遺伝子ごとにその量の変化を調べました。
その結果、ハクサンハタザオの葉で働いていた 17,205 種類の遺伝子のうち、16.7%にあたる 2,879 の遺伝子が季節に応じてその働きの強さを変化させることが明らかになりました。また、春分 ・夏至 ・秋分 ・冬至での日内変化を調べ、7,185 の遺伝子が 1 日のうちで働きの強さを変化させることも明らかにしました。これまで主に実験室環境で研究されてきた遺伝子が、自然条件下で日内変化を示すもの、季節変化を示すもの、変化せずに働き続けるものに分類されました。同研究において、季節変化することが初めて明らかになった遺伝子も多数ありました。
自然条件下では、日長を基準とした春夏秋冬と、気温を基準とした春夏秋冬との間には 1 か月半のずれがあります。つまり、日が一番長い夏至は 6 月下旬、一番短い冬至は 12 月下旬であるのに対して、もっとも暑くなるのは 8 月上旬、もっとも寒くなるのは 2 月上旬です。私たちは、この差を操作した栽培実験を実施し、遺伝子の働きを調べ、自然生育地のデータと比較しました。その結果、野外で観察される遺伝子発現の季節変化は主に温度の変化に応答していることが明らかになるとともに、植物の繁殖や成長にとって、日長と気温の 1か月半のずれが重要であることを示すことに成功しました。全遺伝子の働きの同時測定という最新の分子生物学の手法と、自然生育地の毎週調査という地道な生態学の手法とを組み合わせることが新たな成果につながりました。
■3.波及効果、今後の予定■
同研究は年間を通して網羅的に遺伝子の働きの季節変化を明らかにした初めての研究例であり、その成果として季節変化を示す遺伝子がカタログ化され簡単に検索できるようになりました。植物の季節に応じた生活スケジュールを理解するうえで必須の基礎情報であり、地球環境の変化に対する植物の応答を予測して対応策を立てる上でも重要な情報を与えます。自然生育地での遺伝子機能の研究は我が国がリードしている分野であり、今後、植物を含めた幅広い生物群からのデータ取得が必要であると考えられます。
■4.研究プロジェクトについて■
同研究は、主に以下の研究費の支援を受けました。
◎科学研究費基盤研究 S 26221106 研究代表者・工藤洋)
◎ JST クレスト CREST)植物頑健性領域 JPMJCR15O1 研究代表者 ・工藤洋)および JPMJCR15O2 研究代表者・永野惇)
■研究者のコメント■
自然生育地で生物の生活を丹念に観察するという生態学のアプローチが、遺伝子機能の理解に貢献することを示すことがでたと思います。季節応答を研究するためには、研究材料の取得だけでも最低 2 年かかります。ハクサンハタザオ生育地の地元、多可町牧野と門前の方々の長期にわたるご理解とご協力により、研究の実施が可能となりました。心より感謝いたします。自然界で起きている生物現象の中には、1 年をこえるものがたくさんあります。今後も、分子生物学の最新の手法を導入しつつ、長期研究を展開したいと考えています。
■論文タイトルと著者■
タイトル
Annual transcriptome dynamics in natural environments reveals plant seasonal adaptation. 訳 自然環境下における網羅的遺伝子発現の年間動態が植物の季節適応を明らかにする)
著 者
Atsushi J. Nagano, Tetsuhiro Kawagoe, Jiro Sugisaka, Mie N. Honjo, Koji Iwayama and HiroshiKudoh[京都大学生態学研究センター 永野惇 研究員 研究当時、現 龍谷大学講師)、同 川越哲博 研究員、同 杉阪次郎 研究員、同 本庄三恵 研究員、龍谷大学 岩山浩二 研究員 研究当時、現 滋賀大学助教)、京都大学生態学研究センター 工藤洋 教授(責任著者)]
掲 載 誌
Nature Plants DOI 10.1038/s41477-018-0338-z
【詳細は下記URLをご参照ください】
・京都大学 2019年1月10日【PDF】発表
・京都大学 ホームページ